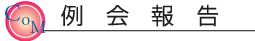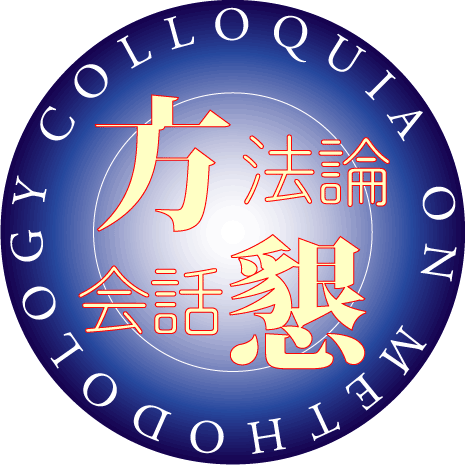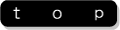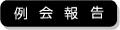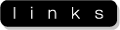第4ク−ル: テーマ〈叙述(2) ―物語―〉
2002年3月例会(3/9、上智大学)
2002年6月例会(6/8、青山学院大学)
2002年7月例会(7/13、青山学院大学)
2002年8月例会(7/27、青山学院大学)
2002年9月例会(9/21、花園大学)
- 松木俊暁 氏 「支配を支えるものとしての〈物語〉─被支配者層から見た部民制─」
- 福島栄寿 氏 「分析者の立場―「信仰」の思想史を考えるために―」
2002年10月例会(10/5、明治大学)
- 池田敏宏 氏 「歴史学としての考古学―その〈物語〉の形成―」
- 森下園 氏 「『構築主義とは何か』第3章「文学とジェンダー分析」を読む」
2002年11月例会(11/2、早稲田大学)
特集「試み―日本古代史における構築主義的アプローチ―」
- 水口幹記 氏 「構築主義(?)三題(含、『構築主義とは何か』第5章講読)」
- 北條勝貴 氏 「『常陸国風土記』行方郡条をめぐる二つの構築過程―再帰的歴史学?の試み―」
2002年12月例会(12/7、青山学院大学)
- 佐藤壮広 氏 「そこに“いる”死者―戦死者の記憶と表象をめぐる試論―」
- 高松百香 氏 「『構築主義とは何か』第7章「構築されるセクシュアリティ」を読む」
2003年2月例会(2/8、早稲田大学)
- 池田敏宏 氏 「月の輪古墳発掘運動とその語り継ぎ」
- 中澤克昭 氏 「『構築主義とは何か』第6章「構築主義と身体の臨界」を読む」
2003年3月例会(3/8、青山学院大学)
- 高木信 氏 「語り物と〈母の悲劇〉」
2003年4月例会(4/12、青山学院大学)
- 工藤健一 氏 「『構築主義とは何か』第1章「臨床のナラティヴ」を読む」
2003年5月例会(5/17、早稲田大学)
各クールとテーマ
報告概要
2002年3月例会
第4クール統一テーマ「叙述(2) ―物語―」について
第3クールでは「叙述」が総括テーマとして選択されましたが、議論の方向は主観/客観の超克へと収斂し、当初想定していた問題群のなかでこぼれ落ちるものが多く出てしまいました。そのため来年度も叙述を検討する姿勢を継続し、なかでも、近年様々な分野で話題となっている「物語」を中心的に扱うことに決定しました。物語については、哲学や文学の分野で以前から多くの研究蓄積がありますし、言語論的転回などとの関連から、歴史学においても議論の対象となってきました。当会では、物語をより広義に「自己経験の分節化」と捉えなおし、あらゆる時代・社会において、人間がなぜ物語を必要とし、生産を続けてゆくのかを考察します。そのなかには、物語生産が準拠する各時代の形式・構造と、それを更新してゆく創造的力の問題、日常生活での安心を求めて経験を分節し物語化してゆく人間の営みの問題、宗教領域においてみられる物語による癒しの問題、人文・社会系学問分野で再評価されている物語的叙述の問題と可能性など、様々な命題が含まれます。
『構築主義とは何か』の輪読について
これまでの例会は、テーマ報告2本を立てて討論を行う形でしたが、6月以後は、テーマ報告1本のほかに、2〜3年のスパンで『GYRATIV@』へフィードバックすることを目的とした、方法論・理論の研究レポートを1本立てることになりました。
最初のテーマとしては、〈構築主義〉をとりあげます。ポストモダン的方法論の代名詞のひとつとして、近年大きな話題を集めている構築主義ですが、いまだ体系的な分析を加えられるには至っていません。そこで当会では、上野千鶴子編『構築主義とは何か』(勁草書房、2001年)所収論考のレポートを手始めに、各学問領域で示される構築主義の可能性と問題点について議論してゆきます。
2002年6月例会
池田敏宏 氏 「歴史学としての考古学―その「物語」の形成について―」
考古学と歴史学は、方法論的にも認識論的にも多くの相違を抱えている。にもかかわらず考古学は、戦前から「歴史像を語るためのもの」「歴史学としての考古学」という方向付けをされてきた。明治の考古学黎明期における二つの流れ―人類学としての考古学/皇国のための考古学は、その後ファシズム期に至るまで国家を正当化する日本人種論・民族論を生産し続けた。それらの言説のうちには、現在の自由主義史観にみえる日本人純血論、縄文文明論などの起源を認めることができる。一方、戦後はマルクス主義という枠組みのなかで歴史学と考古学が共同、統一的な日本史像を描き出しつつ、国民的歴史学運動など評価すべき足跡を残した。しかし、80年代に入ると石母田正や和島誠一など限られた学者・学派の神話化が進み、反対にそれらと逆の方向性を持った(だからこそ今日的価値のある)赤松啓介らの業績が忘却され、マルクス主義的枠組みも形骸化するに至った。今日ではそれらに代わるものとして、プロセス考古学、ポスト・プロセス考古学などの新しい潮流が出現しているが、未だ充分な議論が行われているとはいえない。今後は固定化した「歴史学としての考古学」という物語を脱構築し、恣意的に捨象されてきた言説を再評価しつつ、分散した方法論の共通のプラットホームを構築する努力をしていかなければならない。
2002年7月例会
佐藤壮広 氏 「沖縄の民間巫者が紡ぐ慰霊の語り―戦死者の記憶の現場としての儀礼とことば―」
戦後世代が全国的に増加する一方、戦争経験者が次々と世を去るなかで、戦争の体験と記憶をどのように繋いでゆくかが大きな問題となっている。沖縄では、戦争体験の聞き取りが盛んに行われており、県史、市町村史から字史に至るまで記録が編まれている。それらの文章では、死者は生者による記憶という形で過去化されているが、民間巫者ユタは、その霊的感受性によって戦死者の声を〈聞き〉姿を〈みる〉。記念碑や記念館の建立、戦没者追悼式などのナショナルな場の語りにおいては、死者は「英霊」「国民」といった政治的・共同体的概念のなかに回収されてしまう。しかし、遺族らの私的な求めに応じたユタの口寄せでは、死者は政治的回収を相対化し、血の通った生々しい記憶として立ち現れる。戦死者の記憶の現場となるユタの儀礼、身体は、近代科学的な叙述方法とは異なる、〈生〉に直結した歴史記述のあり方を示してくれる。
2002年8月例会
高木信 氏 「〈システム/不在の原因〉としての怨霊と鎮魂」
記述における他者表象は何らかの暴力性を帯びることを余儀なくされるが、支配的位置を占める勝者=共同体=制度に感情移入する読み方を相対化し、異なる方向性を持つ読みを見出してゆくことは重要な意味を持つ。日本中世の軍記文学には様々な死者が登場するが、祟りをなす〈怨霊〉は過剰な身体を持つものとして表象され、それが勝者によって鎮魂されることでカタルシスを生じ、制度=共同体側に回収され正当化の道具として用いられる。しかし身体化されない〈亡霊〉が、近親者たちの記憶に優しく懐かしい存在として回帰することもある。そして形を与えられ対処法が明確化した怨霊より、分節・表象されることなく、テクストや共同体の周縁を浮遊する亡霊の方が恐ろしいともいえる。死者を怨霊として身体化しない『平家物語』には、清盛をはじめとする平家一門の亡霊が、その表象を支えるものとして構造化されている。潅頂巻を特立する覚一本は、制度側の怨霊化―鎮魂に対して近親者の非怨霊化―鎮魂を対置する。平家一門を鎮魂する建礼門院の役割は、制度的に規定されたジェンダー・ロールではなく自ら主体的に選びとったもの、勝利者の紡ぐ〈たったひとつの歴史〉とは異なる〈もうひとつの歴史〉のモノガタリとして立ち上がるのである。
『構築主義とは何か』輪読の概要(2002年6月〜8月例会)
人文・社会科学系の方法論として流行しつつある構築主義について、上野千鶴子編『構築主義とは何か』を手がかりに検討しようと始めた輪読ですが、3回を数え同書に幾つかの問題点が含まれていることが認められました。
なかでも最大の問題は、ポストモダン的アプローチの最大の特徴ともいえる〈セルフ〉の視点が欠落していることでしょう。とくに第4章・第9章の執筆者は、自らがいかなる位置に立って分析し見解を述べているのかほとんど自覚していないようで、構築主義的視点が批判する純粋客観主義を、ありえない〈透明な記述〉を夢想することで露呈している部分もあります。構築主義的アプローチがいかなるものか、執筆者自身が充分把握できていないのかも知れません。
しかし、議論を行ううえで有効な点も確かにあります。例えば、構築主義に至る、あるいは構築主義における認識論的な整理が厳密に行われていること。文学や歴史学といった分野は認識論とは無縁であることが多いので、自らの方法や思考基盤を問い直すうえでは参考となる記述が多いといえます。
今しばらくは同書の輪読を続け、当会なりに構築主義について見識を深めてゆきたいと考えています。
2003年5月例会
北條勝貴 氏 「第4クール総括: 他者表象・自己言及・物語 ―第4クールから第5クールへ―」
1)『構築主義とは何か』輪読会の成果
方法論懇話会では、2002年度より上野千鶴子編『構築主義とは何か』(勁草書房刊)の輪読を通じて、〈構築主義〉について討論を行ってきた。もちろん、かかる学問的潮流について理解を深めてゆくことは容易ではないが、4月に至ってほぼ全体を読み終えた結果、ひとつの区切りとして以下の問題点を指摘することができた。
一点目は、当会が創設当初より重要な課題のひとつとして扱ってきた、ポジショナリティ、もしくはセルフの問題である。ポジショナリティは、当然対象においても設定することのできる概念だが、研究者の主観において用いるときには、セルフと同様の意義を有することになる。すなわち、自己の対象構成における恣意性・政治性をいかに自覚するか、という問題である。これについては、ポストモダン的傾向の主要な柱として研究者/対象の分離の克服が叫ばれ、叙述に自己告白を組み込むことが一種の免罪符として作用してきた。しかしこのような方法には、第2クールの報告者イーサン・セガール氏がエドワード・ファウラーの著作『山谷ブルース』を挙げ、「私は、山谷よりも、ファオラー個人のことを多く学んだ気がしたものである」(「映画、目撃者、歴史家」、『GYRATIVA』2、2001年、p. 50)と指摘しているように、他者の物語を搾取して結局自己について語り通し、自己の政治性を暴露するつもりがその正当化に終始してしまう危険性が内包される。研究者/対象を直截に分離することはできないが、それを混同することも多くの問題を生じる。それと同じく、認識と叙述(語り)の混同も回避されなければならないだろう。自己について語りたければ、学問研究の体裁を採る必要はない。研究者/対象の区別の克服において重要なのは、第一に認識の問題であり、誤って叙述を優先することが上記の混乱を生じる原因ともなっている。我々が対象構成を行う枠組み、セルフとしての政治性・恣意性を自覚しながら研究を行うことは、これまでの学問的認識に大きな反省を迫り、自ずから対象との接し方・語り方(構成のあり方)も変わってくるはずである。自己言及の程度の深浅・叙述の多少に拘泥するよりも、研究者・対象双方の構築を認識において再帰的にコントロールしながら、個々の実践の場に応じて叙述のあり方を決定してゆけばよいのではないだろうか。 二点目は、言語論的転回以後の大命題である現実あるいは実在の問題、いわゆる「〈テクスト外〉はあるのか?」という問題である。構築主義の最大公約数は、いうまでもなく、「ア・プリオリな存在・事象などなく、すべては言説によって社会的に構成されている」という視点である。そのため構築主義は、客観主義や本質主義の言説と真っ向から対立することになった。しかし赤川学氏が述べているように、「本質などない、ただ言説のみがある」と断定することは、逆にもうひとつの本質主義を出現させてしまうことになる。構築主義が指し示すのは人間の認識の限界であり、折衷的ではあるが、「〈テクスト外〉は存在しうるが、我々はそれを言説を通じてしか認識しえない」との見方に止めておくのが妥当であろう。
三点目はやや総括的だが、理論的整理の問題である。構築主義は認識論批判であるから、客観主義・本質主義との関係、マクロ/ミクロ、個/集団の位置づけなど、ポストモダン的な見解の対立点を多く内包している。構築主義的な認識、叙述のあり方を模索するためには、それらの方法・理論について正確な知識を持っていなければならない。したがって、自らの学問的方法を彫琢してゆくことに自覚的な研究者にとっては、格好の思考訓練になる。実在論的な考え方を注意深く排除し、〈ア・プリオリな存在・事象などなく、すべては言説によって社会的に構成されている〉という視点を(自己への適用も含めて)いかに徹底できるか。すべては、そうした認識論的転換に集約されてこよう。
以上のように、我々が『構築主義とは何か』を通して学んだことは、当会が第1クール以来議論し続けてきた諸々の問題を明確化してくれた。しかし、上記の3点はいずれも哲学的大命題であり、我々は一定の到達点を確認したに過ぎないのであって、決して最終的な解答を得たわけではない。今後はこの成果を各人の具体的関心のもとに活かしながら、さらに理想的な他者表象のあり方、人文・社会科学研究の方法論を探究してゆかねばならないだろう。
2)自己変革と対象の変移―物語としての学史を脱構築することの困難―
第4クールのテーマは〈物語(narrative)〉であった。哲学・文学・歴史学などで議論の対象となってきたこの概念を、より広義に〈自己経験の分節化〉と捉えなおし、あらゆる時代・社会において人間がなぜ物語を必要とし、生産を続けてゆくのかを考察すること。それが、第4クールの問題意識として掲げられている。5名の報告者は、かかる命題にどのように取り組んでいったのだろうか。以下、1)で得たパースペクティヴを参考にしながら、第4クールの各報告を論評し、個々の達成における問題点と課題について考えてゆきたい。
本節では、まず松木俊暁氏・池田敏宏氏の報告を扱う。この二つが、研究者の実践を束縛する〈学史〉という物語(それは、ディシプリンの持つ〈歴史〉でもある)と格闘し、自由を獲得しようとしている点で共通の姿勢を持つからである。
イ)学問共同体レベルでの認識論的困難―松木報告
日本古代史を専攻する松木俊暁氏は、7〜8世紀の氏族が祖先から受け継いだ「名」を通じて王権と接続する現象を、古代社会における自他認識(自己/他者によるラベリング)の問題として捉えようとする。その問題設定に表れた企図は明確であり、残された支配者による歴史=物語がとりこぼしてきた、被支配者層の歴史=物語の抽出にある。そしてその作業は、とりもなおさず、日本古代史研究者自身が〈国家中心的言説〉から脱け出すことを前提としている。日本古代史学界が〈国家〉に著しい関心を示し、マルクス主義歴史学が方法論的には終焉を迎えた現在でもその姿勢を変えないことは、もはや周知の事実であろう。アナール学派の影響を受けて中世史から開始された〈社会史〉は、歴史学の中心軸を国家から社会へ、支配者の政治から民衆の生活へと移そうとした。しかし、古代史学界にはその微弱な余波が伝わるばかりで、本格的な研究は遂に行われなかった。そればかりか、この〈歴史学革命〉は、本流の中世史の方でも一時の流行として終息してしまうことになったのである。その原因についてはすでに指摘されているように、フランスでアナール学派が批判の対象とした政治史が日本では必ずしも主流ではなく、マルクス主義的な社会経済史(一種の構造史)の力の強かったことが考えられる。しかしながらさらに根本的な要因として、主流の社会経済史においてもその基底を形成していたのは実証主義であり、アナールの基底を成していた科学認識論が充分理解されなかった点が挙げられるのではないか。このことは、近年の〈言語論的転回〉をめぐる日本史学界の無反応によって、より一層明らかになったように思われる。その蹉跌を踏まえながら〈新しい古代史〉を目指そうとする松木氏の問題意識は正当であろう。
しかし実際の論理展開は、残念ながら、松木氏の克服しようとした支配者の物語へ、次第に収斂されることになってしまったようである。なぜそうなってしまったのだろうか。氏は、自己/他者のラベリング行為を分析する際、共同体が個人に要請する物語を抽出しようとする。そこには、主体とは常に共同体へ回収されてゆくものである、という客観主義的な認識が強く働いてはいないだろうか。そもそも、共同体とは一体何なのだろう。松木氏の念頭にある共同体概念は、主に石母田正氏によって主導されてきた在地首長制論における共同体概念、日本古代史学界を現在でも強力に支配する〈大きな物語〉に絡め取られているようにみえる。支配者の言説を克服する道具となりうる〈物語〉は、支配の媒介となる共同性創出の道具としてしか捉えられず、松木氏の論旨全体を支配の成り立ち論へと傾けてゆく。結論として導き出されてきたものは氏の意図とは隔たっていたかも知れないが、思考と論理構築に使用されるターム・概念がすべて学史のなかで成立し彫琢されてきたものであるために、そのベクトルに引きずられる形になってしまったのだろうか。支配への収斂に限らず、多様なベクトルを持った物語(アンチではない)の抽出が必要なのではないだろうか。
ロ)個人レベルでの倫理的困難―池田報告
池田敏宏氏は、元来、2001年度の第2クール〈研究者と対象との距離〉の報告者として『GYRATIVA』2号に執筆するはずだった。報告テーマは、考古学のディシプリンがいかに成立するか、とりわけ「真の考古学は歴史学でなければならない」とまで宣言する〈歴史学としての考古学〉が、どのように姿を現すかを跡づけるものであった。この報告は極めて丹念な学史分析であったが、静態的・客観的になりすぎたため、第4クール〈物語〉において再び考古学における学史の意味を問うことになったのである。ここで池田氏は、これまでの学史を鳥瞰する姿勢を一変させ、戦後考古学における和島主流派ライン・赤松異端ラインの形成過程(和島の正当化における赤松の排除の構造)、そのひとつの結節点であり、池田氏の考古学の理想型を形成する〈国民的歴史学運動(月の輪古墳発掘)〉をめぐる言説分析へと踏み込んだ。それはとりもなおさず、研究者としての自己のポジションを探す旅、ライフ・ヒストリーとしての学史分析であったといえる。それは、方法論的には客観主義的方法から主観主義的方法への移行であるが、自己を規定する物語としての学史の分析から、より内面的・倫理的な、研究者としての〈核〉を形成するものの探究への転換であり、実現における精神的負荷も大きかったものと推測される。
このような池田氏の転換は、これまでの当会の議論の方向性に合致する歓迎すべきものだが、会全体に新たな問題も提起することになった。それは、研究者をより強固に規定するのは、議論の推移としての学史(自己を束縛しているように感じられるもの)ではなく、学史のなかから自らが発見し構築した研究者としての原風景(自己を突き動かしているように感じられるもの)なのではないか、ということである。考えてみれば当然のことなのだが、研究主体としての自己が常に批判対象としている問題群よりも、むしろ理想化された風景こそが政治的・恣意的に歪曲されているのである。私たちは、研究主体としての自己の存立基盤こそをみなおし、そこで絶対化された価値観が基準となって行われる、信じたいもの/批判したいものの無意識における選択過程を自覚しなければならない。このことは、現実を隠蔽し統制する物語のマイナス面と、現実を整理し次段階へのモティベーションとする物語のプラス面とが、強固に、分かちがたく結びついていることを意味する。池田報告があらためて気づかせてくれたこの問題は、当会全体の共有財産となった。しかし本当の問題はその先にある。自己のポジション形成の起点をも相対化するその作業の向こうで、私たちはどうのような態度をもって研究に臨めばよいのだろうか。別の原風景をよすがにさほど変わらぬポジションの再構築を図るのか、それとも正当性(内面における恣意的特権化)を失った動機をそのまま引き受け続けるのか。そもそも、研究における〈正当性〉はなぜ必要なのだろうか。私たちは、〈それから〉どうするのか?
松木報告も池田報告も、研究主体を無意識に規定するディシプリン(もちろん学史ばかりでなく、〈研究者〉を再生産する教育・研究機関、学会などの人的関係を含む)の強固さをあらためて気づかせてくれた。我々は内外両面におけるその影響力を自覚し、それを本質的なモティベーションとして無批判に肯定するのではなく、自己決定に参照しうる一要因に止めておく努力をしなければならない。さもなければ、学界における政治的ヘゲモニーの獲得努力を、自己の問題意識と錯覚する〈正当化の物語〉の生産は後を絶たないだろう。
3)他者表象における絶望と可能性―他者とは誰か、現実のありかは?―
続いて、福島栄寿氏・高木信氏・佐藤壮広氏の報告をとりあげる。3氏の報告はそれぞれ他者表象のあり方を議論の核として持っているが、現実をいかに考えるかなどの対立点を抱えている。ともに1)で指摘した構築主義の問題に重複しているが、実際の報告の場ではそれらに関して充分な討論を行うことができなかった。個人的にではあるが、ここで3氏の対立軸を整理し、第5クールが継承すべき課題についてまとめておきたい。
イ)分析者の倫理と保証―福島報告
2001年のアメリカ・同時多発テロ事件とその後のアフガニスタン報復攻撃、イスラエル・パレスチナの武力闘争、イラク戦争などの国際動向は、我々に〈価値観の異なる他者〉をどのように受け入れてゆくか、受け入れることができなければこの世界は崩壊してしまうという深刻な問いを突きつけた。これら一連の事件に衝撃を受けた福島栄寿氏は、近現代史の研究者であり宗教者でもある自らの成り立ちを跡づけながら、他者について非暴力的に語る方法を模索している。ポストモダン的視野における分析者/対象の関係とは、対象が分析者の認識によって構成されることを前提としている。ならば、対象について語るためには、まず自己について語る必要がある。いやむしろ、対象への言及/自己への言及は同義であるといってもよい。ここには、他者表象を論じる際、分析者のライフ・ヒストリーが提示されなければならない必然性が示されている。しかし、自己について語る限り、自己を正当化するために他者表象を利用する危険性は常に伴われる。それは、自己の政治性・恣意性を暴露するようにみせながら、他者を搾取し自己を正当化する行為に他ならないのである。1)で掲げた、自己/対象と認識/叙述の混同の抑止の問題が、ここで大きく立ち現れてくる。岡真理氏の論考などを手がかりに福島氏が示した抑止の方法は、「どこまでも自らの立場のようなものを『脱臼』させていく」ことである。私も第3クールの報告「〈書く〉ことと倫理」において、エコロジー的叙述のあり方として、「自然のために書くこととは、自然と人間との関係についての正確な知識に基づき、自然との個別的・集団的・全体的交流の原体験に支えられながら、人間利益の維持・促進に属するあらゆる言説、イデオロギーを徹底的に解体する方向で叙述すること」だという提言を行った。他者との関係において自己を徹底的に相対化してゆくこと、それは極めて重要かつ困難な行為だと思われるが、同時に他者表象論の今日的限界をも表しているといえるだろう。
福島氏は報告の最後に、近代思想史上における暁烏敏(明治・大正期に活躍した真宗大谷派の僧侶・思想家。国粋主義的な言説を展開したことから、戦後批判の対象となる)の位置づけを事例に、暴力性を排しつつ共約不可能性(完全なる共感・意志疎通のありえないこと)を前提としながら行う、具体的な他者表象のあり方を提示している。他者を利用あるいは断罪することで自らの〈正義〉を主張するのではなく、思想や言説をその人間のありように即して理解すること――。このような傾向は、近年現代思想や人類学を中心に強くなりつつあるが、人類学など(そして、福島氏が「ポスト構造主義以降の宗教学」として紹介する宮川英子氏の立場も)が反証可能性を持った他者の監視の目に晒されているのに対し、過去の他者を対象として構成する歴史学には、その権力を抑制するための枷が存在しない。したがって歴史学の場合、〈その人間のありように即して理解すること〉ができたという確証が、どのようにして得られるのかということが問題となる。いかに他者に配慮し慎重を期した見解であろうと、それが誤解に過ぎなければ、否応なく暴力性を伴うことになってしまう。対象との直接的二者関係を構築しえない学問において、共感と理解の保証は、一体どこに求めうるのだろうか。やはり「脱臼」に求めざるをえないのだろうか。福島氏の報告には、解決困難な重い問いかけが残されることになった。
ロ)浮遊するシニフィアンの回収―高木報告
高木信氏の報告は、『平家物語』における〈亡霊〉――支配者=勝利者によって鎮魂され、共同体の枠組みに回収されてしまう〈怨霊〉ではなく、テクスト/共同体の周縁にあって記号を破砕する前記号的存在――という視点から、他者表象の問題に切り込んでいる。氏のいう〈亡霊〉は、文学で時折用いられる、〈浮遊するシニフィアン〉という概念に近似しているかも知れない。記号学においては、記号はシニフィアン(signifiant、音声イメージ)/シニフィエ(signifie、概念)によって構成される。ソシュールの定義によれば、相互前提的な両者の結びつきは、決してア・プリオリではなくむしろ恣意的である。しかしその恣意的結びつきが強固であればあるほど、ステレオタイプの意味が再生産され構造は強化されてゆくのだろう。それに対して〈浮遊するシニフィアン〉とは、両者の結びつきがほぐれ、特定のシニフィエに固着しない存在(関係可能性?)となっている。そのため、既成の構造の再生産には寄与しない。氏はこの点を評価し、「カタルシスを呼ばない」「反物語・反歴史・反共同体のラディカル」と述べている(しかし、この「反」=アンチという表記は、構造の基本形である二項対立的関係を構築してしまう。高木氏の本意に即した形でいいかえるなら、「脱物語・脱歴史・脱共同体」との表現が適当だろうか)。非暴力的な他者表象の可能性を探究するうえで、この概念のあり方は(理論的には)大変示唆的である。しかし認識論的には、シニフィエを持たないシニフィアンを、我々は認識できるのかという疑念が残る。仮にある特定のシニフィアンが浮遊していたとしても、それは我々が認識した時点であるシニフィエと結びつけられてしまう。そうでなければ、我々の耳にはイメージを結ばないノイズが響くのみとなろう。したがって問題は、両者を連結しシーニュ(signe)として認知する、主体としての私の恣意性にあることになる。それについて自覚して初めて、意味の方向性を既成の状態からズラすことができるはずだが、高木報告はあくまでテクストの内部について語っており、主体について語ろうとはしない。それは、高木氏が〈豊饒なる現実〉の世界を否定していることとも関係がある。氏は、他者表象における暴力性は不可避であるとしているが、〈亡霊〉を近親者の供養によって鎮魂されるものと意味づけていることからすれば、直接的二者関係(自己と他者が何ものをも介さずに向き合うこと。人類学の関根康正氏などが、オリエンタリズムやコロニアリズムを克服する方法として掲げている)には回避の可能性を認めているようである。しかし、もし現実=テクストの外部を認めないとすれば、〈他者〉とは誰にとっての他者であり、一体どこにいるものなのだろうか。〈浮遊するシニフィアン〉である亡霊が出現する「テクストの縁」とは、テクストと現実(社会に生きる私という主体)との境界ではないのだろうか。それらもすべてインターテクスト的に考えるというほどには、高木氏の論理・表現は徹底されていない。
高木報告には、言語論的転回以後の〈現実〉をどのように把握するか、という極めて大きな問題も関わってくるのである。
ハ)豊饒なる現実の所在―佐藤報告
高木報告が拒絶した〈現実〉と、決して切断できない関係にあるのが佐藤報告である。佐藤壮広氏が重視するユタの語り、ユタによる戦死者の表象は、国民国家日本や沖縄県という体制的共同体へ回収されないベクトルを持つ。そして、彼女たちの持つシャーマンとしての自己投機、死者への〈絶対的〉共感(死者の身体と化すこと)に支えられている。この語りのあり方は、高木報告の提起した〈亡霊〉の概念とも、福島報告の提案する〈脱臼〉の方法とも通底する。しかし、〈個〉の多様性を示す〈豊饒なる現実〉そのものである点で、また内的論理においては語る主体のアイデンティティーを喪失している点で、高木報告とも福島報告とも異なっている。とくに後者の問題は、宗教を内的に読解する方法の探究において、決してブラックボックス化してはならないことである。ユタの語りは、敗戦体験や反戦のシンボルに祭りあげられる死者(=他者)表象をズラしてゆく可能性を持つものだが、しかし、そのズラしにおける個=主体の内実について佐藤氏は多くを問わない。ズラされる方向としての沖縄の宗教的世界(それも一枚岩ではなかろう)は、超越論的なもの=自明のものとして前提されているように私にはみえる。物語る主体としてのユタの政治性、恣意性について問わなければ、やはり死者表象を〈聖域〉の彼方に疎外してしまうことになるのではなかろうか。
しかし、佐藤氏の指摘する〈怪談(幽霊話)〉の重要性には、歴史概念について再考するうえで興味深いヒントが隠されている。巷間に突如として現れては消えてゆく、多くの世間話、都市伝説の類。そのなかには、現代的問題意識には容易に回収されない、物語る主体の不分明な過去の記憶が込められている。それこそが実在する〈亡霊〉であり、編成物ではない歴史(それはもはや、〈歴史〉とは呼びえないかも知れないが)としての可能性を秘めているのではなかろうか。それがど現代社会に位置づけられ特定のシーニュとなることに抵抗し、〈亡霊〉のままであり続けられるようにする叙述は可能だろうか。ひとつの手がかりは、主体としての〈集団〉概念を再考することにあるだろう。明確な意志を持った近代的個の投影された集団ではなく、集団としての集団――個々の実体的要素に還元できない関係の網の目としての集団概念について、考えるべきではないだろうか。それは、例えば勃興期の社会学が明確に持っていた〈集団〉の考え方だろう。近代性を批判するポストモダン的主体こそが、実際には多分に近代的個を反映した実存主義に染まっているといえなくもない。土居浩氏によれば、こうした見方は、人類学の田辺繁治氏らが重視する〈実践コミュニティ論〉の集団概念に近いという。しかし私は、社会関係のなかの個ではなく、社会関係としての集団そのものに注目したいのである。
4)第5クールへ
以上、簡単ではあるが、第4クールの各報告に論評を加える形で総括してきた。最後に、そこから明らかになった問題点、第5クールへ向けての課題についてまとめておくことにしよう。
一点目は、池田報告で明確となったセルフの深化である。これまで私たちは、ディシプリンの束縛を自覚し、自己の恣意性を問うためにセルフに論及してきた。しかし、私たちの問題意識の根底にあるモティベーションこそが、自己正当化の物語として構築されたものだったのである。それは究極的に、セルフとは何なのかという問いへと向かう。学問する主体としてのセルフを積極的に評価するとともに、そのセルフのありようをより厳密に深くみつめてゆくことが重要であろう。
二点目は、個を主体としない物語の可能性である。つまり集団の物語であるが、この集団の意志は個の持つような明確な問題意識へ還元することはできない、近代的主体としては考えることができない集団である。そこで語られる物語は、整理と正当化という二つの機能を超越するベクトルを持つのではないか。人間にとっての物語の意味を考えるためにも、かかる〈集団〉概念・〈物語〉概念は重要な鍵となるだろう。
第5クールの各報告は、以上の問題点・課題に、個々の具体的問題関心のなかで応えてゆくことになろう。その新しい展開に期待したい。なおここで行った総括は、松木俊暁氏が自らの例会報告を克服するために書かれた新たな論考、高木信氏がクールの最後に行われたもうひとつの例会報告、福島栄寿氏が上記の報告を踏まえて最近公にされた論著を対象とはしていない。この点ご寛恕を願うとともに、第4クール報告者諸氏の新たな挑戦に敬意を表したい。