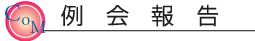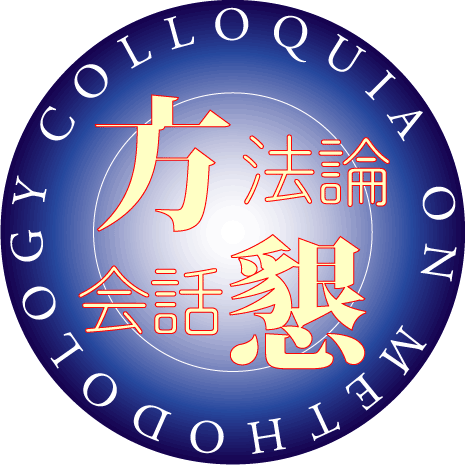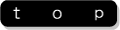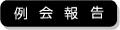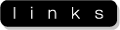第3クール: テーマ〈叙述〉
2001年4月例会(4/14、上智大学)
2001年5月例会(5/5、上智大学)
- 方法論懇話会編『日本史教科書』編集会議 (1)
2001年6月例会(6/2、上智大学)
2001年7月例会(7/7、上智大学)
2001年9月例会(9/1、上智大学)
2001年10月例会(9/22、佛教大学)
2001年11月例会(11/10、青山学院大学)
2001年12月例会(12/8、明治大学。宗教的言説研究会との共同例会)
- 斎藤英喜 氏 「井筒俊彦『コーランを読む』―第一章、第二章を中心に―」
- 北條勝貴 氏 「藤原京造営に至る環境改変の正当化ー伐採儀礼・天皇即神・都城ー」
- 師茂樹 氏 「叙述における主観/客観の克服―仏教学における叙述を中心に―」
2002年1月例会/合宿(1/13〜14、長野市立 篠ノ井公民館・中尾山温泉 松仙閣)
2002年2月例会(2/9、早稲田大学)
2002年4月例会(4/13、早稲田大学)
2002年5月例会(5/11、上智大学)
各クールとテーマ
報告概要
2001年4月例会
第3クール統一テーマ「叙述」の設定について
まずは第2クール統一テーマ「研究者と対象との距離」の総括討論にて、池田敏宏、兒島峰、若林晴子、イーサン・セガールの各氏より追加報告と問題点の指摘がなされ、議論のまとめが行われました。総括では、対象との距離のとり方は個々の学問・研究者によって異なるが、その異質性をこそ大切にしてゆくべきこと、学問的制度によって固定化された対象=他者を、研究者としての自己を解体しうる根源的他者へ回復してゆくことの必要性が確認されました。
そして、その距離のとり方=関係の構築において不可欠の問題として、第3クール統一テーマ「叙述」が設定されました。方法論懇話会では、自らの政治的・社会的スタンスを明らかにすることで客観性を保証する叙述方法をとってきましたが、近年、こうした態度とは一見対照的な物語的叙述方法、対象に埋没する叙述方法が注目を集めています。第3クールはこれらの叙述を逐一検討し、第2クールの議論を踏まえ、あるべき叙述の理想像を模索し、記述することの権力の問題を追究してゆくことになりました。
2001年6月例会
師茂樹 氏 「都会に雨がふるごとく―松本史朗「縁起について」における主観の表現―」
批判仏教の流れに属する松本史朗氏の如来蔵思想批判を題材に、主観/客観の二項対立を克服した叙述スタイルの発見を志向する。具体的には、客観的な研究には客観的な叙述スタイル、主観的な研究には主観的な叙述スタイルが必要との立場から、松本氏の「縁起について」に見る日記形式に注目し、他者との共有を拒否する主観表現が公開されることの意味を追究する。また、「雨」に関する松本氏の主観的イメージをサルトルの『嘔吐』と比較しつつ、厳然とした秩序―分節化―カオスの対立構造から、松本氏がなぜ如来蔵思想を拒否するのか、その主観的な意味を探る。
北條勝貴 氏 「二項対立のむこうに―〈実践〉概念の彫琢による自然/文化図式の克服―」
人間の思考を根本的に規定してきた弁証法的思考図式を拒否し、マルクスの本源的関係態という関係項から、自然/文化の二項対立を克服しようとする試み。人文・社会・自然科学のすべてが、主体の実践を構造革新の原動力として、歴史変動の要因として重視する傾向にあることを指摘、主観主義/客観主義の対立への近代的執着が無意味であることを確認する。そのうえで、レヴィ=ストロースが追求し続ける「自然の理法との一体化」に賛意を表し、倫理・道徳の再構築による主体の変容を経た、新たな学問的実践の可能性を模索する。
2001年7月例会
野村英登 氏 「研究表現としての訓読」
日本の中国学が特徴的に持つ技術「訓読」は、漢語の概略的な分節や、明治以前の研究蓄積との関連においていまだ有効な研究方法である。しかし、学問研究の国際化やインターネット化において、日本人以外の研究者やより広範な読者層を排除してしまうという問題が生じている。学問研究の社会への還元という面からも、中国学の記述方法に関する公的な議論が必要であることを提言。
三浦具嗣 氏 「歴史の中の翻訳―歴史叙述を考える上で―」
「翻訳」という営為を、クリステヴァの間テクスト性、クーンの共約不可能性という二つの視点から、ハクスレー『進化と倫理』の中国における翻訳『天演論』の成立を通して考える。古今東西の思想を援用した『進化と倫理』はヨーロッパ世界が東洋へ、『天演論』への翻訳は中華世界がヨーロッパへ、それぞれ自己の文明社会の動揺を背景に視線を向けたことを示しているかのようである。しかしそれは、それぞれのテクスト世界の同心円的拡大にすぎず、眼差しの先には自己の鏡像があっただけである。このような異パラダイム間における共約不可能性は、歴史家の歴史叙述にも思い問いを投げかけている。
2001年9月例会
方法論懇話会編『日本史教科書』の編集会議について
各項目の執筆者ら14名に森話社の大石良則氏を加え、執筆者の顔合わせ、執筆内容の構想報告、内容調整について意見交換がなされました。扱われる題材は、緑色の考古遺物から喚起されるイメージを扱う認知考古学的研究、歴史学における〈人物〉認識と政治・権力との関係を扱った近代史、〈和服〉という身体化された日本人の境界を問う人類学的研究など多岐にわたり、極めて内容豊かで刺激的な本が出来そうです。
2001年10月例会
ついに初めての京都例会が実現、稲城正己氏と斎藤英喜氏のご協力を得て、20余名の参加した大変な盛会となりました。議論も活発に行われ、「来年度から恒例に」との声も聞かれました。また、例会報告の後には、新しく『日本史教科書』の執筆者に決まった中尾瑞樹氏(「日本的仏教の多様性」を担当)からも、一般に知られていない密教修法を題材に、常識的な日本仏教観を打破する構想報告が行われました。
工藤美和子・稲城正己 氏 「死者の言葉・生者の言葉―菅原道真の願文をめぐって―」
「願文を『書く』ということ」(工藤氏)
平安朝の追善願文のうちで、菅原道真が起草した文章を史料を通じて具体的に検討、1)時間的経過に沿ってものごとの概略を記した物語的記述形式、2)会話体の採用、3)仏教用語の儒教・道教的言説による言い替え、などの諸特徴を指摘。これらは、仏教的知識が貴族社会に充分普及していなかった平安初期の情況に応じ、仏教的教養を身に付けた道真が行った独自の表現(文学的プラチック)であると位置づけた。
「願文について『書く』ということ」(稲城氏)
工藤報告を基底に、願文というテクストが生成され法会で読まれる情況の背景に、〈報恩〉コンテクスト、〈利他〉コンテクストが作用していることを解明。道真を含む9〜10世紀の文人貴族が、権威化された漢籍や日本の先行作品に刻まれたコンテクスト、コードをハビトゥスとし、それらを意図的にズラせていく文学的実践を行っていたと指摘。そうしたテクストを読む現代の研究者には、テクスト作成者が想定した読者として自己を一致させることも、対象化して客観的に扱うことも可能であるとした。
斎藤英喜 氏 「いざなぎ流太夫―近世陰陽師研究から『宗教者』の内在的記述をめざして―」
近世陰陽師に関する外在的研究によって、呪術を行う博士系宗教者と神楽を担う神職系宗教者の二系統があり、それらが技術的に融合した明治期にいざなぎ流の誕生が位置づけられた。しかし、太夫の祭文や法文によれば、双方の技術の根源はともに金巻童子という始祖的シャーマンに収斂されており、研究者の獲得した認識とは異なる歴史・世界観が浮かび上がる。そうした「当事者たちの経験のリアリティ」中にこそ、真の「歴史や社会のコンテクスト」があるのではないか、それをいかに発見しいかに記述するかが重要であるとの問題提起。
2001年11月例会
北條勝貴 氏 「〈書く〉ことと倫理―自然の対象化/自然との一体化をめぐって―」
人類学の分野では、研究対象として構成される他者―異文化にどのように接するか、それらの抱える社会問題についてどのように対応するかという倫理的問題が様々に議論されている。近年では、a)主体の復権と自覚、b)豊穣なる現実の再認識、c)支配的言説の解体・表象の解放、d)他者への共感・感情移入がキーワードとして掲げられているが、これらは人類学だけでなく、人文・社会科学全般に共通する課題である。対象となる過去の人間存在と時間的に隔てられている歴史学は、そこよりの反対証言を封殺している点で大きな権力を持つが、倫理についてほとんど問題としてこなかったため、歴史修正主義の跳梁を招くことになった。自然を扱う歴史学は対象と存在論的にも隔てられているが、自然存在と共感することの可能性はディープ・エコロジーなどの実践によって示されている。自然について語る諸史料は、自然との直接的交感に基づく人間否定のベクトルを、次第に人間中心主義的に変質させてゆく傾向を持つ。自然を扱う歴史学は、生態学などによる自然と人間との関係についての正確な知識に基づき、自然との個別的・集団的・全体的交流の原体験に支えられながら、人間利益の維持・促進に属するあらゆる言説・イデオロギーを、徹底的に解体する方向で叙述しなければならない。
2001年12月例会
同日は宗教的言説研究会とのジョイントで行われました。重複するメンバーもかなりいるのですが、いつもとはひと味違った顔ぶれが揃い、活発な議論が展開されました。今後も機会があればこのような試みを続け、いずれはシンポジウムのようなものも開きたいと考えております。
師茂樹 氏 「叙述における主観/客観の克服―仏教学における叙述を中心に―」
1980年代に始まった<批判仏教>の潮流を、1)文献学的手法・2)インドへの指向・など仏教学の伝統を受け継ぎながら、主観性/客観性についての新たな問題提起を行ったものとして捉えなおす。とくに、「仏典理解という実践が既に主観的なものであるから、仏教学は客観的な立場では議論できない」とする松本史朗氏の見解は注意される。確かに、研究者が隠蔽された自らの主観を暴露し、その問題意識と方法論を自覚的・明示的に叙述へと組み込むことは、ポストモダン的学問情況において重要である。さらに、松本氏が論文に日記的文体を挿入し曖昧模糊とした心性を綴るように、問題意識や方法論へ昇華する以前の雑駁な主観、構造化される以前にこぼれ落ちてしまう主観を叙述の材料とすることも必要ではなかろうか。しかしそこには、研究者同志で共有しうる議論の場、客観的結論を拒否する姿勢も含まれているので、それらを私たちが許容すべきか否か、未だ多くの問題が残されている。
2002年1月例会
方法論懇話会編『日本史教科書』掲載論文最終報告会
- 第1部 日本史学のメタヒストリー
- 見城悌治 氏 「『日本史』という安息地とその陥穽」
- 第2部 歴史学的アプローチの最前線
- 1) 文献史料の読み方
- 稲城正己 氏 「歴史学とテクスト分析―〈事実〉と〈フィクション性〉」
- コラム1) 歴史と物語
- 三浦具嗣 氏 「歴史の物語り論」
- 2) 考古資料の読み方
- 山川純一 氏 「色のもたらすもの―考古学資料からみた緑色の心性―」
- 3) 絵画資料の読み方
- 工藤健一 氏 「絵画資料を読む」
- 4) 歴史像の構築
- 内藤亮 氏 「法隆寺と斑鳩寺―史実と伝承の間―」
- 5) コンピュータと電子テクスト
- 師茂樹 氏 「コンピュータと電子テクスト」
- コラム2) コミックと古典
- 森下園 氏 「コミックと古典」
- 第3部 開かれる過去/解体する現在
- 1) 生活文化の相対化
- 中澤克昭 氏 「割箸の文化史」
- 北條勝貴 氏 「環境破壊と日本文化―自然との新たな関係をめざして―」
- 2) 宗教文化の相対化
- 斎藤英喜 氏 「その者、青き衣をまといて‥‥―神話と歴史の脱領域―」
- 佐藤壮広 氏 「シャーマニズム・アニミズムと現代―基層信仰の現代的展開―」
- 3) 政治文化の相対化
- 及川栄二郎 氏 「戦争と責任―歴史修正主義と社会の保守的傾向―」
- 兒島峰 氏 「ネイションの身体化―衣服と〈日本人〉―」
- コラム3) 単一民族神話の解体
- 池田敏宏 氏 「日本民族論の背景にあるものは何か―コロボックル論争を中心にして―」
- 4) 日本史の相対化
- 森下園 氏 「日本における世界史と世界における日本史」
- 三浦具嗣 氏 「オリエンタリズム」
2002年2月例会
三浦具嗣 氏 「翻訳の可能性と不可能性の間で」
固有の文化・社会・環境などと密接に絡みあって生成され、機能している言語を翻訳することは、本質的には不可能である。しかし、現実に多くの書物が翻訳されていることは確かであり、それらがいかなる機能を担っているのかについては考えてみる必要がある。翻訳という現象は、読み・解釈の介在する一種のコミュニケーション、〈言い換え〉として考えることができる。この<言い換え>は、複数の言語圏の存在を前提とするが、地域をアイデンティファイの対象としての言語=国語で区切ることができるのは近代である。その意味で翻訳は近代的な問題であり、また翻訳自体が国語の生成・血肉化に大きな役割を果たしてきた。19世紀という近代において、ヨーロッパで東西の思想を縦横に引用し『進化と倫理』を著したハクスレー、中国でそれを翻訳した厳復は、真理が東西の区別なく共通であるという普遍主義を確信した。19世紀的な敬意と共感が、20世紀的には軽蔑と侮蔑になる幻想に過ぎなかったとしても、その翻訳が本質的翻訳ではなかったとしても、翻訳は歴史のなかで特定の役割を果たしたのである。
野村英登 氏 「中国学の学術論文に訓読は必要か?」
中国学の研究論文においては、訓読の使用が確固たる制度として存在している。漢籍を引用する際に、原文に現代語訳が付されるのではなく訓読が載せられるわけだが、これは外国語を使用する学問においては特殊な状況である。当然、その背景には前近代から連綿と繋がる漢学の伝統が横たわっているが、それに対して、中学・高校教育では漢文の授業時間は激減し、私立大学での受験科目からも多く除かれているという現状がある。中国学専攻でない限り、訓読のできない研究者というものも多数存在しているわけである。中国学の論文が対象としている読者は、極めて限定されているということになるが、それは学問のあり方として適正なのだろうか?
2002年4月例会
工藤美和子 氏 「叙述―菅原道真の願文をめぐって/文人官僚が書くということ―」
従来の道真研究においては、願文はほとんど扱われていないか、もしくは彼の仏教信仰を示すものと位置づけられている。しかし、願文の叙述は僧侶・貴族らの人間関係において文人官僚が担う創造的実践=言説形式を生み出す作業であり、必ずしも個人の信仰に直結するものではない。道真の願文は後世のそれに比して具体的かつ長文であり、儒教・老荘に関するタームも頻出する。それらは従来のコトバにより仏教の新たな世界観を解説した結果であり、彼にはそれをなしうる知識・能力が備わっていたことを意味する。〈報恩〉をテーマに描かれたそれらの願文は、それまで天皇・国家の安泰を祈願していた仏教を、個や家をも対象にしうる宗教へ組み換えてゆく規制力を持っていたと考えられる。
稲城正己 氏 「叙述―菅原道真の願文をめぐって/研究者が書くということ―」
道真の願文は、国家仏教を個や家を対象としうるものへ組み換えただけでなく、現世を三世(前世・現世・来世)へ、列島を広大な仏教的世界の一角へと拡大/相対化する、時空認識の変革を促した点でエポック・メイキングな言説であった。これをスコールズのコミュニケーション図式(書き手と読み手の間にコンテクスト・メッセージ・接触・コードの四要素が介在する。伝達に際し読み手の想像力が必要になればなるほど、その言説は文学性が高いということになる)で読み解いてみると、道真と研究者自身の属する時代・世界が異なるうえ、背景に複雑な仏教的コンテクストが作用するので、歴史叙述として行うにもかかわらず極めて文学性が高くなってしまう。とくに、四要素に何を配するかによってコミュニケーションの様相はまったく違ってくるが、その作業は研究者の恣意性に満ちている。また、我々はこの願文を対象として構成することによって、幾らかの客観性を留保しているわけだが、その作業によって脱落してくるものも多い。例えば、四要素を客観的読むことはできても、願文に表現されている意図―報恩を通して仏教に帰依し悟りを開くという誓願―にはまったく応えておらず、メッセージの伝達は行われていないことになる。研究者がそれらも含めて読み/書くことを可能にする方法には、現時点で二つのあり方が想定される。ひとつは、仏教の各宗派でなされている宗学・教学的な読み/書き、誓願をそのままに継承する自己投棄の方法である。ただし、これはコンテクストをまったく無視して行われるため、多くの誤認を含んでしまう。もうひとつの読み方は、仏教の縁起理論などと共通の考え方を持っているポストモダン思想(ポスト構造主義)を援用することだが、論理の共通性を基盤とするために原理主義に陥り、例外や多様性を捨象してしまう危険もある。そうした弊害を克服する新たな読み方、宗教的言説に適した読解/叙述の方法について模索中である。
斎藤英喜 氏 「方法としての〈ドン・ファン〉―「構造分析」から対話記述によって何が可能となったのか―」
いざなぎ流の祈祷師たちを客観主義的観点から記述することは可能だが、彼らが宗教的実践を通して向き合っている世界は、そうした記述方法では捉えることができない。カルロス・カスタネダの〈ドン・ファン〉シリーズは、いざなぎ流の祈祷世界を内在的に記述する理論的な根拠となりうる。『ドン・ファンの教え』は二部構成になっていて、第一部はドン・ファンとの出逢いから修行体験を描いたフィールド・ノート、第二部はそれに対する構造分析となっている。しかし、それは人類学者が行う一般的な意味での構造分析ではなく、ドン・ファンの教えそのものが持つ論理的思考を根拠に、客観的に説明されたものであった。それに対して対話的記述の部分には、時間を追ってカスタネダの体験、ドン・ファンの教えに対する認識が深まってゆく過程が記述されている。カスタネダは幻覚性植物によって得た非日常的体験をドン・ファンに語り、ドン・ファンはその特定の単位を強調して道筋を付け「独自な合意」を形成してゆく。カスタネダの体験はその対話のなかで深められ、さらにそれを記述することで師の教えをもう一度点検し、一層の深まりをみせてゆく。対話的記述とは物語の方法なのである。かつて私は、いざなぎ流の太夫から学んだ究極の天神法を記述することを拒んだが、それはインフォーマントの秘密を漏らさないという研究者の倫理に関する問題ではない。「それを無闇に口にすれば、お前が学んだことはすべて力を失う」という太夫の教えに従い、呪術の内在的な力に近づく記述法を採ったのである。
2002年5月例会
中澤克昭 氏 「問題提起―〈叙述〉までの道程―」
言語論的転回を含む〈歴史の物語り論(narrative)〉は、素朴実証主義や素朴実在論を批判的に克服することを目指したものだが、客観的事実に対する危機意識のない盲信が、いまだに歴史学界を支配している。このような状態では、歴史修正主義の主張する国民の「物語(story)」にも対抗することはできない。方法論懇話会では、年報1号の当初から、問題意識と叙述の関係、言説編成行為の恣意性と政治性に自覚的であろうとしてきた。そうしたスタンスは、必然的に自らとの研究対象との距離、関係を問うことにも繋がった。年報2号の兒島論文が、「研究対象に対して限りなく好意的なまなざしを注いでも、対象との距離そのものを解消することにはならない。ある対象に接近するための方法が、排除しなければならない存在を構築することであってはならない」と述べるように、研究者と対象との距離とは、記述・叙述の問題そのものなのである。3クール目の議論においては、これまでの経緯を踏まえたうえで、1)〈読解し書かれたものである〉史資料をさらに読解・叙述するという、歴史学的実践の二重・三重の表象の問題、2)主観/客観という二項対立の克服、3)新たな叙述形式の模索、4)分かりやすさ(一般性)とディシプリンの対立、5)媒体の多様化、などの課題が指摘されてきた。今回の報告者たちは、これらに対してどのような解答を出してゆくのだろうか。
総括討論の流れ
3クール目の報告・議論は、「叙述」をテーマとして掲げながら、方向性としては主観/客観の克服に収斂していた。例えば三浦報告は、客観主義的対象構成ではマイナスの意味合いしか持ちえない〈翻訳〉という現象・行為を、当事者の主観を対象化することによって読みなおした叙述法で、客観主義的立場に立った克服のアイディアである。師報告は、主体の内在化する仏教学という学問において、主観であることを自覚的に用いた批判仏教を手がかりに、主体のポジション、主観のあり方に可能な限り自覚的になることで客観性の保証を目指そうとしている。北條報告は、認識や叙述に持ち込まれる対象への主体のあり方を理論的に把握することで、客観主義的対象構成に沿った主体的記述を模索した。稲城報告は、テクストのメッセージを受け取る主体的実践としての叙述法を、やはり客観主義的立場から目指そうとしている。斎藤報告は、対象との関係がそのまま認識と記述を律する主体的叙述法を提起しているといえる。これらの試みは、問題意識に直結する主体性をめぐって、客観主義的対象構成・叙述法と、主観主義的対象構成・叙述法の間を往還している。問題は、それらの方法が二項対立的関係にあるのではなく、問題意識のあり方―何を明らかにし、何を書きたいか―によって多焦点的に配置されうるということである。どれが最も優れた方法かという見方ではなく、どれでもよいという相対主義でもなく、各々の問題意識に即した最良のあり方を求めて、相互に交流し補完しあうことこそが重要なのではないか。〈物語り〉への注目は、多様性のなかでの精度・論理を求めるためのひとつの手がかりである。