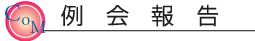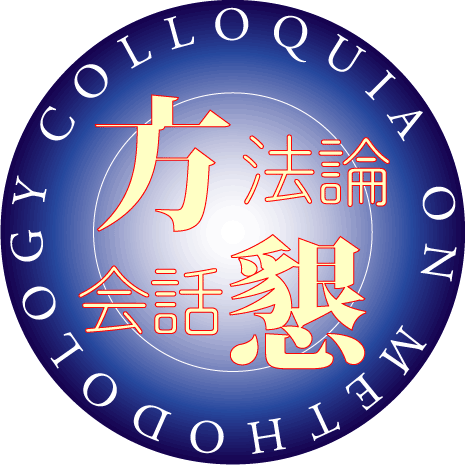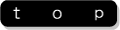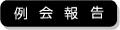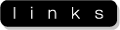第6ク−ル: テーマ〈記憶〉
2004年度前期例会(2004/9/18〜19、マホロバマインズ三浦)
臨時例会(2004/11/28、花園大学)
- 平野寿則 氏 「食行身禄の救済・治国論」
ミニ研究会(2005/3/19、東洋大学白山校舎)
- 池田敏宏氏(考古学:(財)とちぎ生涯学習文化財団埋蔵文化財センター) 問題提起「記憶のメカニズム—認知科学の視点から」
- 三浦宏文氏(インド哲学:東洋大学東洋学研究所) 報告1「記憶・想起・知識ー時間論から方法論へのアプローチ」
- 土居浩氏(地理学・民俗学:ものつくり大学) 報告2「記憶(論)の外部委託ーstand alone complex」
2005年度前期例会(2005/9/17〜18、布引温泉・国民年金健康保養センターこもろ)
テーマA: デリダ研究の現状と課題
- 師茂樹氏「仏教学におけるデリダの受容と問題点」
- 北條勝貴氏「デリダと言語論的転回後の歴史学」
- 稲城正己氏「柄谷行人のデリダ—『探究』Iをめぐって」
テーマB: 記憶
- 須田努 氏「人斬りの村になるまで—19世紀、民衆運動における暴力の語られ方—」
- 平野寿則 氏「食行身禄の救済・治国論(仮題)」
- 総括・討論(司会 師茂樹氏)
各クールとテーマ
報告概要
2004年度前期例会
第6クール統一テーマ「記憶」について
第5クール統一テーマ「構築主義とナラティヴ」は、私たちに対象を捉える新しい視野を与えてくれるとともに、構築主義のそのままの形での援用が、人文諸分野に多くの方法論的齟齬を生じることを自覚させた。とくに、同会でも常に大きな問題となっている「実存」の把握が放棄されることには、研究者としてのセルフにおいて受容できないものを抱える報告者もあった。存在さえもがテクストに還元されてしまうというのなら、実存を構築している言説とは何なのか。ポール・リクールらポスト・モダンの先駆者たちは、常にそのことに気づいていた。「記憶」……第6クールではこれを統一テーマに掲げ、存在を構築する物語として多角的に分析、構築主義をより深く理解・消化してゆくことを目指す。
須田努 氏 報告1「人斬りの村になるまで—19世紀、民衆運動における暴力の語られ方—」
【討論の感想】 京浜急行に乗り、三浦海岸駅に降りたころは、車内から聞き始めた桂三木助の「芝浜」はサゲに近づいていた。歴史プロパーではない方々の前での報告は久しいぶりである。余計な雑念を持たないようにと、噺を聞きながら、晩夏の三浦の道を歩いていった。
第6クール前期のテーマ「記憶」に関しての池田敏広さんの問題提起は、認知心理学をベースにしたものであった。このあとのわたしの報告はどうしましょう、といった戸惑いが一気に膨らんだ。
わたしは、暴力論とこの語られ方、といったことを19世紀の日本を舞台に考えようと、している者である。今回の報告は、18世紀の伝馬騒動と19世紀の甲州騒動(詳述はさけたい)を比較しつつ、暴力に直面した人びとが、これをいかにうけとめ、記録し、記憶していったか、ということを問題にしてみた。
報告では、記録→語り→記憶という回路をつくってみたが、これは、「あまりにも直線すぎるのでは」といった批判をいただいた。「記録に直結しない記憶があるのではないか」との意見もだされた。
わたしは、報告の準備過程において、史料を読み込む際に、記録と記憶との差違をいかに見いだすか、といったことを意識してみた。しかし、これはどうもうまくいかない、と結論にいたり、両者不分明のまま、報告をおこなった。この点を批判されたわけである。
また、「当時の人びとが暴力をどう読んでいたのか」「暴力は人びとによってどう読み込まれていたのか」「文芸作品、随筆などのでの暴力の描かれ方はどうか」との質問も出された。これは、わたしも意識していた。しかし、時間がたりず、百姓一揆史料(これ自体も文芸作品として側面を有しているが)を読み込むことで精一杯となってしまった。近い将来、文芸作品・随筆なども扱っていきたいと考えている。10月には、講義の準備もあり、『世事見聞録』を暴力といった視座から読み込んでみた。歴史事象として論理化していくには、もういくつかの手続きが必要であることがわかってきた。
さらに、「百姓一揆史料は、なぜ一人称で書かれているのか」といった意見をいただいた。これは、まったくわたしが意識していなかった問題であり、ふるえがおこった。百姓一揆史料を物語論として考察していく上で、とても重要な指摘をいただいた、と思う。
方法論懇話会会員みなさんのご意見、学問領域を超えての方法論上の議論はとても刺激的であった。寝不足の連続と、翌日の仕事のため、夜のコンパにおつきあいできなかったこと、例会二日目の研究会に参加できなかった点、心残りであった。
翌午前、仕事に行く途中、知り合いの勤める新宿紀伊国屋に立ち寄り、さっそく認識論心理学に関する書籍を買い込んだ。
嶋内博愛 氏 報告2「怪火の読まれ方—煉獄の誕生と「燃える人」伝承—」
火や狐火、人魂など、光を伴う夜の怪異については、はたして現実に発生する現象なのかどうか不明な部分もいまだ多い。そのためこれらは、一般的にはオカルト的な怪異現象の一種とみなされ、現代の日本社会でたとえば「昨夜見た!」という証言が聞かれることはまずない。しかし、民俗調査として各地を訪問しお話をうかがうなかで、「以前、あの道のところで狐火を見たことがあるよ」といった話ならば、今でも少なからず聞くことができる。報告者の知る限りにおいては、ヨーロッパにおいてもさまざまな怪火目撃譚が同じように散見され、さまざまな命名がされている。そのうちのひとつが、本報告の主たる題材でもある「燃える人」(その概要については後述)である。ちなみに、本報告では「怪しげな光」、「光を発する怪異現象」の総称として「怪し火」または「怪火」という語を用い、燃える人はその下位概念という位置づけである。ドイツ語圏で怪火を指す呼称としてもっとも一般的なのは、イルリヒト(Irrlicht)だ。「惑わす、困らせる」を意味する動詞irrenの語幹に、「光」を意味する名詞Lichtが連結したものである。英語では一般的にはウィル・オ・ザ・ウィスプ(will o’the wisp、「藁束のウィル」の意)が用いられるが、ラテン語にその源を持つイグニス・フテュウス(ignis fatuus)も使われる。イグニス・フテュウスなる語は、元を辿れば、「愚かな」(fatuus)「火」(ignis)を意味し、ドイツ語のイルリヒトも同様の語からの直訳だろうと推測されている。フランス語やイタリア語でも、一般的にはそれぞれフ・フォレ(feu follet、「狂った火」の意)、フオコ・ファトゥオ(fuoco fatuo、「狂った火」の意)と呼ばれ、これらの表現もラテン語同様の構図がみえることから、西欧の諸言語における怪し火の名称は、ラテン語から各国語に翻訳・導入されていったのではないだろうかという推測が立つ。いうまでもなくラテン語は、20世紀初頭までカトリック教会の公用語であり、母語としての話し手が皆無であるにもかかわらず、西欧文化のなかでは突出した位置を占めていた言語だ。それゆえ、怪し火の名称にこんなにも色濃いラテン語の影響がみられるという事実は、怪し火を知覚した際に採用された説明原理の来歴を語っていると考えても、あながち的はずれではないだろう。つまり、ラテン語使用者、より正鵠を期して言えばカトリック教会の聖職者が、空中を浮遊する怪火現象を現実から切り出し、命名した張本人だったのではないだろうか。
ところで、ドイツ語圏の各地では、19世紀から20世紀前半にかけて、さまざまなザーゲ(いいつたえ)を収集および編集・出版するという営みが盛んに行われた。その結果、じつに膨大な数の伝承集が編まれている。本報告では、そのうち約100冊(ないしはコレクション)を通覧したうち40程度の中に散見される、「燃える人」(Feuermann、直訳すれば「火の男」)および怪し火をモティーフとする類話、約350編を基礎的なデータとして使用し、怪火現象に関してどのような語りがされているかについて考察した。
燃える人に付随するイメージにはいくつかのパターンがある。たとえば、「存命中に犯した違反のために、昇天できない死者」であるとか、「燃える姿で現世を彷徨い続ける死者で、生者に祈ってもらえば昇天できる」といったものだ。つまり、「昇天」や「救済」、「祈り」といった宗教的モティーフと、燃える人は切り離すことができないのである。それは、とりもなおさず、「燃える人」伝承形成の背後に、他界観についてのキリスト教的イメージが隠れていることを示唆している。報告者は、こうしたシナリオを想定している。
この仮説を検討するため、後半では、キリスト教的論理における死者=他界観についてみていった。
ル・ゴフによれば、煉獄の誕生は資本主義の成立と密接に結びついているという。従来の天国と地獄という二項対立的な他界観が、煉獄の導入でドラスティックに変容し、それにともない死者復活の教義的意味も変化していった、と。
しかし、こうして構築されていった他界の情景は、16世紀の宗教改革によって大きく動揺する。たとえばハムレット。清教徒であったはずの彼の苦悩、すなわちプロテスタンティズムによって否定された煉獄の解釈をめぐる苦悩は、同時に、シェイクスピアと同時代人の苦悩ではなかったか。あるいは、ルターは『煉獄の無効宣言』において、煉獄とともに怪し火の存在も一蹴する。逆説的にこれら煉獄にまつわるエピソードを読み解けば、脈々と育まれてきた煉獄のイメージが、すでに宗教者の思惑を越えて、民衆の心の奥底に自明の存在として刻まれていたことを読み取ることができはしまいか。
「燃える人」伝承がキリスト教世界において果たした役割とは、いったい何なのか。ひとつには、この伝承が、死者の居場所を生者の世界に提供している点だろう。伝承がもつ寓意性・説話性を通して、死してなお人はキリスト教の枠内に留まることが許されると、「燃える人」伝承では語られる。もうひとつには、伝承に埋め込まれた互酬関係である。伝承を語る主体(民衆=話者)と語らせる主体(教会=作者、訳者)、そして語られる主体(死者=登場人物)、これら三者が紡ぎ上げるメカニズムが、民衆世界において教会が支配的な役割を担うための大きな戦略として機能していったのではないだろうか。
語られ、記録された記憶・伝承は、エリート文化と民衆文化とがせめぎあい、鎬を削る界面を活性化させ、教会が民衆文化に根づくための大きな戦略の一翼を担っていたかもしれない。だが、民衆は、エリート層から発信される情報を、自らの思考枠組みを駆使し、彼らなりに理解・操作し、さらにそれを自分たちの言葉で言い換えてもいた。その言い換えられた言葉のひとつが、まさしく、「燃える人」伝承だった。これが、本報告の終着点である。
【討論の感想】 合宿の際、さまざまな分野の方々の研究にふれることができ、とても刺激的な2日間でした。参加する機会を与えてくださった方法論懇話会の皆様に、心から感謝の言葉を申し上げたいと思います。ありがとうございました。「感想を」ということですので、このときの経験をふまえ、記憶についてその後私が考えたことを、以下、“書き殴って”みたいと思います。
人間の脳をコンピューターにみたて、記憶を「保存されている情報」と考えてみるとします。
個々人の脳内に蓄積されている情報は、当事者によって発信されなければその情報が「ある」ということは、外部からはわかりません。保存されている情報は、発信されてはじめて他者に認知可能な〈記憶〉になる、ともいえましょう。とすれば、とあることがらについて本人はすっかり忘れてしまっていたけれど、ふとしたきっかけで「記憶が甦ってきた」場合は、そこではじめて情報が〈記憶〉として立ち上がったと考えることができるかもしれません。あるいは、何かショッキングな〈出来事〉が、個人の中で整理されず、アモルフな情動のまま留まっているならば、それは、〈記憶〉ではないともいえるかもしれません。しかし、はたして脳はたんなる「情報の容器」なのでしょうか。脳内に格納された情報が変化することはないのでしょうか。ひとは、自らの脳内に蓄えられた情報に働きかけることはないのでしょうか。たとえば、インタビューの現場をみるとどうでしょう。インタビューは、インタビュアーがインフォーマントから情報を引き出す場ではなく、インタビュアーとインフォーマントとがある物語を紡ぎ上げる共同作業の現場ではないのでしょうか。
このように考えてくると、人間の脳をHDDにみたてることには限界があるように私には思えます。誰かから聞いた話、伝聞にすぎなかった話を、いつしか、あたかも自分で体験したことのように思いこんでしまったとしても、本人は「記憶している」と思っている場合も想定できます。にもかかわらず、〈記憶〉として発信された途端に、それは他者には「ある人が心に留めていた、記憶」として伝わります。受け手は、その情報だけでは、それ(=ある人が語った〈記憶〉)が「偽」(※注:「偽」といっても、もちろん、どこかに絶対的な「真」があって、その裏返しとしての「偽」、という意味ではありません)かどうかを判断することはできません。第一、本人は「真」と確信しています。本人がどう思っているか。これは尊重しなければならないでしょう。
個人ですら「偽の記憶」が作られてしまうくらいですから、複数人によって記憶されている〈出来事〉というのは、またさらにややこしくもなります。社会的な記憶において、〈出来事〉について書き込まれる/ている場は、複数人の脳内(共時的に、通時的に)、あるいは時間軸に左右されない(またはされにくい)、モノ(たとえば文章や造形など)などが挙げられそうです。モノは「記憶そのもの」なのか、あるいは「記録」、「記憶のインデックス」なのか。その答えは私にはわかりません。というより、コンテクストによりけりだと思っています。
こうした多様な現実に直面して、フィールドワーカーはどのようにふるまったらよいのか。「唯一の答え」というものは、今の私にはありません。今この文章を書いていても、自分の中でまだきちんと言語化されていない部分が多々あります。体験が〈記憶〉としてアウトプットされる過程と同じように、アモルフなアイディアからは、おそらく、考えれば考えるほど異なった見解が自分の中で生まれるでしょう。つまるところ、これは、今後私がさまざまな経験を重ねていくなかで考え続けていかなければならない、果てしない課題なのではないでしょうか。
三浦宏文 氏 報告3「過去はいかにして認識可能か—インド実在論学派の認識論における記憶観—」
本発表では、インド正統派六派哲学の一つ、ヴァイシェーシカ学派の記憶観に関して考察した。具体的には、同学派の学説を体系化したプラシャスタパーダ(6世紀)の著書『プラシャスタパーダ・バーシュヤ』の認識論における過去認識の問題を中心に検討した。
同学派の時間論では、時間は基本的に「過去」と「それ以外」とに2分割して整理され、過去の認識に関わるのは記憶と夢とされる。
まず記憶とは、1) 徴証をみることや願望や追想の確認のために(生じた)自我と心の特殊な結合のために、あるいは、2) 強烈さや反復や留意といった観念から生じた心的な潜在印象のために、見たり聞いたり経験したりする対象において(生じる)、残余の確認と願望と追想の原因である〈過去〉に関する知識である。この記憶が対象とする〈過去〉は、「残余の確認、願望、追想、憎しみの原因になる」という特徴を持つ。これらに共通していることは、すべて継続的なものであるということである。
次に夢は、1) 強い心的潜在印象、2) 体調不順、3)不可見力の三つの原因から生じるとされ、その原因ごとに様々な形の夢が例示され、整然と分類されている。
夢が過去を対象とする知識である理由は、それが原理上リアルタイムで経験することができないからである。なぜなら夢の最中は、それが夢であるかどうかということを判断することができないからである。それが夢であったことがわかるのは、その当人が夢から覚めた時である。したがって、夢という認識でとらえられた「夢の知識」は、「夢の終わりに際して生じる夢の知識」としてしか成り立たない。そして、それは思い起こす「想起」という形でしか知りえないのである。したがって、感覚器官の総体が睡眠によって作用をいったん停止したとしても、過去の知識の継続が確認されるので、記憶と同列に扱われるのである。言うまでもなく、「過去の知識の継続の確認」とは、現象的にはまさに想起をさしている。そして、ここでもやはり「知識の継続」がポイントになっている。
結局、プラシャスタパーダの説によれば、記憶は以前に経験した事柄すなわち〈過去〉を対象とする知識である。ただし、この〈過去〉というものは、なんらかの形で継続する知識の原因でなければならない。言い換えれば、継続する知識を生み出しえなかった場合、それは〈過去〉たる条件を欠くのである。したがって、この記憶の理論では、例えば「客観的な過去がどこかに存在する」という想定はできない。それについての継続的な知識が確認できなければ、それは〈過去〉ではあり得ず、たとえ存在を否定しえなくとも、少なくとも知ることはできない。故に、「継続的な知識の確認」すなわち思い起こすことのできるものだけがプラシャスタパーダにとっての〈過去〉でありうるのである。
また、もう一つの重要な点は、記憶(および夢)は、あくまで知識の継続が基本になっているということである。その継続とは、言うまでもなく「現在」までの継続である。したがって、「過去の知識の継続の確認」は、必ず現在時に行われることになる。ということは、すなわち記憶も夢も現在経験として成立しているのである。
したがって、プラシャスタパーダの認識論においては、〈過去〉を知ることは、現在経験として、知識の継続を確認することによって可能となるのである。言い換えれば、現在経験としての記憶と夢によってのみ〈過去〉は知りうるのである。つまり、〈過去〉は、現在から完全に独立してはおらず、客観的な「過去自体」は存在しない。
このようなプラシャスタパーダの認識論は、いわば「現在一元論」という側面があるといえる。したがって、インド実在論学派であるヴァイシェーシカ学派の記憶観は、この「現在一元論」的な認識論によって基礎づけられているのである。
【討論の感想】 初めての例会参加で、しかもあれよあれよという間に報告者を任じられ(笑)、少し戸惑う所がありましたが、充実した議論が出来たように思います。
まず報告者としては、2時間近い議論を伴う発表というのは正直な所初体験であり、発表前はどうなることかと戦々恐々としておりましたが、会員諸氏の活発な発言・議論によりあっという間に規定の時間を過ぎていましたこれは、私に取って新鮮な経験であり、大変刺激になりました。
次に、討論参加者としては、普段聞き慣れない分野の発表ばかりなので、まず発表内容を把握することにかなり苦しみましたが、慣れてくると、私の図々しい性格もあり、わからないなりに積極的に議論に参加できたと思います。ただ、私に取っては、紹介してくれた師氏以外すべての方が初対面であったので、議論の際名前がわからず受け答えの際戸惑うことがありました。できれば、ネームプレートをおくとか、最初の発言の時のみ名前と所属をいう等の処置がとられると、初めての参加者も戸惑いがないと思います。
全体的には、大変満足の行く例会でしたが、私自身がそうであったように、当会の例会の趣旨やシステムに関する理解度に関して参加者間にかなりの温度差があった感は否めません。これは、もちろん私を含めて参加者個人の責任に帰することが大きいのでしょうが、より会の趣旨やシステムを納得した上での報告・参加が得られるよう、参加者への連絡や報告者への意思確認に関して努力すべき点はあると思います。
土居浩 氏 報告4「記憶の外部委託—頭の外のこと—」
【前口上】 今回、私が報告を仰せ付かったのは、「記憶」に関する論考(土居浩2003「トポグラフィティの民俗誌」岩本通弥編『記憶』朝倉書店)を発表したことが大きな理由である。『記憶』と題された論文集に収められたこの論考については、北條氏によるコメントが当会MLに流された(記事番号8: 2003-12-05)。
今回の報告では、文化研究における記憶論に心理学的記憶論は適用可能であるか、その点を中心に批判的検討を行った。事前研究会@関東において、近年の記憶論がいう「記憶」とは一体何なのか、その定義がほとんどされないままに議論されている現状認識が共有されたことを受けての試みである。
近年の記憶論ブーム以前から、記憶にこだわりその機能を分節し把握を試みているのは心理学になるだろう。とはいえ私見では、心理学の記憶論を、そのまま文化研究に接続するのは困難である。ここでは、心理学のテキストが教える「記憶」の素朴な三段階論、覚える[記銘]/覚えておく[保持]/思い出す[想起]の区分を取り上げ、批判的検討を行う。
まず以下の2点が指摘できるだろう。
イ)文化研究的記憶論は「想起」をキーワードとするが、はたして心理学的記憶論がいう[想起]と同義か。記憶の三段階論でいうなら、むしろ[記銘]段階における取捨選択に注目するのが文化研究的記憶論ではないのか。
ロ)構築的に記憶を考察する文化研究的記憶論においては、[記銘]段階の構築性をこそ論じるのであって、[想起]段階の構築性はじつのところさほど注目されているとはいえない。
この指摘と、[土居2003]における「記憶の歴史化/歴史の記憶化」を関連させれば、[記銘]段階の構築性を論じる傾向が「記憶の歴史化」であり、 [想起]段階の構築性(=融通無碍さ)を論じる方向が「歴史の記憶化」と仮に対応させることができる。それぞれ[土居2003]の事例を用いて検討しておこう。
【記憶の歴史化をめぐって】 記憶の[想起]を問題とする、と設定しているにも関わらず、実際に検討しているのは記憶の[記銘][保持]ではなかったか。
土居が示した福大明神の事例を用いて検討しておこう。従来(近代以降の研究者に限らず近世の地誌も含めて)問われてきたのは、現在は紀貫之として祀られている福大明神とは本来何だったのか、である。これは、[記銘/保持/想起]の三段階論でいうなら、「福大明神=紀貫之」として[想起]されている現状に対しての異議申し立てと押さえることができる。この立場からすれば、じつは『古今著聞集』に「福大明神=狐の尾(によりダキニ天を祀る)」起源譚が[記銘]されており、[保持]段階において混乱が生じ、「福大明神=ダキニ天(ひいては稲荷)」が「福大明神=紀貫之」に変わってしまったのだ、との歴史的経緯が説明されることになる。この従来の立場に対して土居は、福大明神社が保持する「福大明神=紀貫之」説を示す縁起(『福大明神縁起並和歌』)に注目した。この縁起は「福大明神=紀貫之」説を[記銘]するアイテム(のひとつ)とみなしうる。少なくとも土居が福大明神の祭祀者である「Bさん」(@[土居 2003]での表記)に尋ねた際、「貫之さんとして祀っている」「Bさん」自身の根拠として示したのがこの縁起だったのである。単純に表にして整理すれば、次のようになるだろう。
『古今著聞集』 『福大明神縁起並和歌』 「福大明神=紀貫之」 [記銘] [保持(=混乱)]or[記銘] [想起]
従来の立場が縁起を[保持]段階つまりは混乱が生じた原因として捉えるのに対し、土居は新たな[記銘]段階として捉える。縁起として[記銘]されたことが[保持]されたことにより、「福大明神=紀貫之」が[想起]され続けているのだ。
以上から導かれるのは、[土居2003]の福大明神を検討した部分は「記憶の歴史化」作業そのものである、ということだ。「福大明神=紀貫之」として [想起]される「記憶」の経緯を、縁起成立期における奉納者・冷泉為村による諸活動の中に位置付け「歴史化」したのである。そこで焦点化されているのは [記銘]段階にほかならない。
ここで片桐雅隆2003『過去と記憶の社会学』世界思想社が阿部安成ほか編1999『記憶のかたち』柏書房を例に挙げつつ言及した「歴史学の研究」、すなわち「統一的、独占的な集合的過去を構築する作為的な営みとしてのコーメモレーション(記念行為、記念行事)への見直し」へ対しても、「記憶」三段階の類比を続けるならば、それはコーメモレーションの契機という[記銘]段階を問うものとしてみなすことができよう。じつはこの動向は、何も「歴史学の研究」に限らず文化研究全般のいわゆる「近代の発明」論について指摘しうる。
【歴史の記憶化をめぐって】 土居自身が「民俗学の独自性を主張しうるのではないか」とした「歴史の記憶化」作業とは、これまでみたような[記銘]あるいは[保持]に注目するよりも、むしろ[想起]に注目するものである。[土居2003]においては、十念の辻および日降坂について考察した部分である。
十念の辻の事例で示した、「史実の伝言ゲーム」モデルと「史実の三題噺」モデルとの対比は、じつは「記憶」の三段階論が上手くあてはまるかどうかで区別することも出来る対比である。もちろん合致するのは「伝言ゲーム」モデルであり、「三題噺」モデルでは[記銘/保持/想起]という三段階論が想定不可能だ。可能なのは[想起]段階のみである。「三題噺」モデルでは、データがすでに存在していることが前提されている。そのデータをそれなりに組み合わせることで、ある程度前後の筋が通るような物語へと編み上げられた結果が、様々なトポグラフィティ(=場所にまつわるおはなし)なのではないか。
考えて見れば、[記銘/保持/想起]の三段階論とは、コンピュータにおける情報の[符号化/貯蔵/検索]つまり、外界の刺激情報をある種の符合の形に置き換え/それらを蓄え/必要に応じてそれらを取り出す一連のプロセスに置換可能であるから判るように、発想としては情報が白紙にどれほど精確に/間違えて記されるのか、を基本的イメージにしているのだ。これは心理学における手法=実験を想定すれば当然のことである。ならば情報が白紙の状態であることを想定困難な歴史学・民俗学的対象においては、「記憶」の三段階論を適用するのは困難であると言わざるをえない。
改めて「三題噺」モデルから考えるならば、「伝言ゲーム」モデルは転倒した事態である。一度構成された物語が事後的に「かつてあったこと」としてそれなりの位置付けがなされると、「伝言ゲーム」モデルがきわめて説得力のあるものとして成立するのである。おそらくその説得力が最強のものが、いわゆる「史実」であり「歴史」なのである。その観点で再検討するならば、福大明神社・十念の辻・日降坂をめぐるそれぞれのトポグラフィティの質の違いがモデル適用の可否を決定している、との見通しが得られるのである。端的にはそれぞれの副題が示すように、考証と縁起(福大明神社)・書かれたもの(十念の辻)・語られたもの(日降坂)となる。もちろん、「伝言ゲーム」モデルがより適用しうる福大明神社と、「三題噺」モデルがより適用しうる日降坂へと、トポグラフィティの質の違いは基本的には滑らかに連続しているし、特に語られるトポグラフィティにおいては論考で挙げた事例が全てではない。その意味でもそれぞれの質はまさに錯綜しているし、どこかで明確な断絶線を引けるものではない。
【今後の課題/記憶の協同化への注目】 記憶の構築性を検討してきた今回の報告では、じつは記憶の社会性・集合的記憶と呼ぶ場合の「集合的」となる契機については未検討であった。その課題に対しては新たな素材をもとにして、後期例会に臨みたい。
なお討議を受けて、特に以下の二点を反省点として特記しておく。
- 学問領域で区分する有効性を考えた上であえて記すが、報告後、敏感に反応したのは人類学者である。歴史学者はどう反応してよいのか戸惑っているように感じられ、学問領域を超えて議論を共有し損なった点が残念である。もう少し互いの事情を理解した上での議論を積み重ねる必要がある。
- 討議参加者の一部から「沫のような議論をよくできるなぁ」との感想(嘆息)を頂戴したことからも明らかなように、その「沫のような」の対極に想定された「実証的」な手続きを求める研究主体の態度こそを問い直すまでに至らなかった。
2005年度前期例会
以下の会員諸氏によるblogを参照: