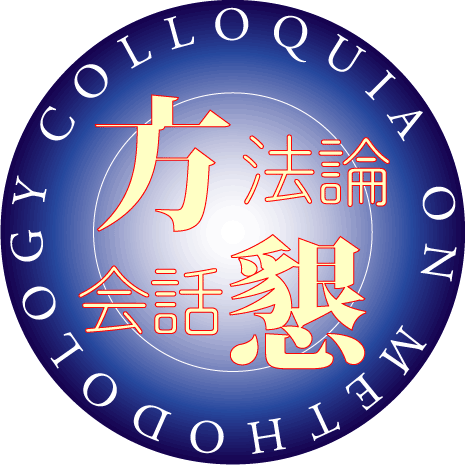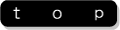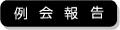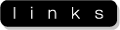創刊号: 特集「歴史と問題意識」
(Special Issue: Historiography and Critical Mind)
- 2000年5月刊、96ページ
- 頒価1300円(会員900円)・品切れ
「なぜその研究を行うのか?」 これは、自らの研究という知的営為の根源に関わる問いである。この点に無自覚であることは、研究の自己否定に等しい。しかし、我々自身、ともすれば、それぞれの〈専門分野〉というカテゴリーの中で、研究対象の選択を自明のことと認識してしまっているのではないだろうか。〈問題意識〉こそ、すべての研究の原点に位置するものであり、それに自覚的であることによってのみ、自己の研究を単なる独善から救い出すことが可能となるであろう。
以上のような認識に基づいて、『GYRATIV@』創刊にあたり、我々は〈歴史と問題意識〉という共通のテーマを設定することとした。それぞれの研究の原点を確認することから、本誌の歩みをはじめようと考えたからである。
本号に掲載された論考は、昨年1年間の方法論懇話会における議論の集成である。執筆者はそれぞれ、自らの対象とその選択について、能うかぎり誠実に向き合うことに努めてきた。しかしながら、充分な考察に達しえていない点も多々あるかと思われる。読者の方々から、忌憚のないご批判をいただければ幸いである。(工藤健一「問題提起」より)
目次と概要
工藤健一「問題提起」
(KUDO Ken'ichi. Addressing the Issues.)
北條勝貴「言語論的転回と歴史認識/叙述批判―現状の整理と展望―」
(HOJO Katsutaka. Rethinking History through the "Linguistic Turn".)
アナール学派をはじめとする〈新しい歴史学〉の潮流以降、歴史学という学問分野の枠組みを相対化し、理論的に激しく動揺させた問題に、主にアメリカを舞台に惹起した〈言語論的転回〉による歴史認識・歴史叙述批判がある。それはポスト・モダニズム的テーゼに触発された素朴実証主義批判で、ダントやホワイトによって歴史の物語性が暴露されたことに端を発し、ラカプラの主導により伝統的歴史学やアナール学派的社会史への激しい攻撃へ成長した。これらのなかで示された議論の大半は、歴史学者の経験主義、自己の分野のみにしか通用しない閉鎖的価値観・基準に基づいており、言語論的転回の根本的批判力には答ええていなかった。この論争を流行に終わらせることなく、歴史学が自らの方法を批判する認識論的基盤を、隣接諸科学の診断基準にも対応しうるものとして確立してゆくことが急務である。
森下園「日本における西洋史研究の問題点−異文化理解のための他者認識の欠落―」
(MORISHITA Sono. The Study of Western History in Japan: Problems and Proposals for Better Understanding of the Cultural Other.)
現在の日本における西洋史研究は、西欧の研究者と比肩しうる成果をあげつつも、「日本人としての視点」の欠落や「日本人向けの研究」が圧倒的という問題点がある。理論や研究手法を導入して、一見欧米とそっくりな西洋史研究を構築しても、その成果が欧米で受け入れてもらえなければ一方通行に終わってしまう危険性がある。言語も歴史も異なる欧米との文化的背景の相違を双方が認めた上での交流こそが、いま求められるものではないだろうか。
三浦具嗣「問題意識と叙述の戦略―厳復の思想史的位置の再考を題材に―」
(MIURA Tomotsugu. Strategies for Describing History: Constructing and Deconstructing Historical Discourse.)
歴史学は歴史を「書く」「叙述する」学問分野である。今日の歴史に関する哲学は、かつてのように歴史の内在的意味を探求するような類のものではなく、あくまで歴史を「書かれたもの」「叙述物」として把握してなされる分析哲学でなければならないだろう。歴史を叙述する際にはまず「どう書くか」、すなわち叙述のプロットを準備せねばならない。そして次に「なぜそう書くか」、つまりなぜそのプロットを選択したのかについての自己確認が必要であろう。その二つの選択は、当然の事ながら先行研究という名の先行歴史叙述群のネットワークを参照する中でなされなくてはならない。そして叙述行為を通じて、歴史学者は歴史叙述のネットワークに介入するのである。フーコー的な文脈における「言説」の定義が「語られたこと」「書かれたこと」の総体だということを考えてみれば、歴史とはまさに言説だと言うことが可能である。歴史叙述という営為は、歴史という言説の編制の場に参加するということであることを確認しておきたい。
水口幹記「日本古代における中国文化受容研究の方法試論―国文学の方法をいかに歴史学に援用するか―」
(MIZUGUCHI Motoki. On the Methodology of the Study of Reception of Chinese Culture in Ancient Japan.)
日本の古代文化を探る方法として、出典研究がある。しかし、この方法は主に国文学を中心に行われているものであり、歴史学に援用するには注意深くその問題意識を観察しなくてはならない。本論では、小島憲之氏の『上代日本文学と中国文学』を検討材料に、問題意識を検討し、「その目的(問題意識)は、作者(述作者・選者)が表現した言葉を正しく理解するためである」ことを指摘した。しかし彼の問題意識には、1)作者(述作者・選者)と読者、さらに作品を含めた三者の関係性の曖昧さ、2)歴史的視点の希薄さ、3)「なぜ」を問う姿勢の欠如が感じられ、全面的には首肯できず、これを乗り越えるのが歴史学の立場からの回答であると考える。このように相手の利点と問題点をあえて指摘することによって、転じて自己の分野の限界と可能性を見極めることができ、この作業を感情論抜きで積み重ねていくことこそが本当の「学際的研究」への近道であると信じている。
工藤健一「日本中世史研究と『自然』」
(KUDO Ken'ichi. "Nature" in the Study of Medieval Japanese History.)
すべて、人間の営みは根底的なレベルにおいて自然環境からの影響、制約を受けざるを得ない。近年、世界的規模で進行する環境問題の深刻化にともない、様々な分野で自然環境をめぐる議論が活発化している。しかし、日本の歴史学研究においては、未だ、こういった問題に対する取り組みは必ずしも充分なものとは言い難い。小論は、自然・開発・心性といった概念を手がかりとしながら、これまでの日本中世史研究における「自然」の位置付けを探ることにより、歴史研究において「自然」を対象とする際の問題点、方法等についての私見を提示したものである。
中澤克昭「遺跡・言説・発達―城郭研究のメタヒストリーから―」
(NAKAZAWA Katsuaki. A Discourse on the Study of Castles.)
〈遺跡はつくられる〉といわざるをえない。昨今の天守閣建造もその一例である。それを推進している一般の城郭観は、近世以降に形成されたもので、それ以前の各時代に固有の城郭観など認識されてはいない。しかし、言説としての「城郭」を探ると、例えば中世社会においては「城郭」という言説が、強い政治性を帯びて使用されていたことがわかる。そうした中世の城郭観と現在の城郭観との間には大きな差異がある。しかし、その差異の自覚こそ不可欠なのではないだろうか。
池田敏宏「総括:〈歴史と問題意識〉をめぐって」
(IKEDA Toshihiro. Concluding Remarks.)